
RISE English Course 英語カレンダー(無償版)を公開しました
![]() 現在、2013年3月―4月のカレンダーを無料でダウンロードできます!
現在、2013年3月―4月のカレンダーを無料でダウンロードできます!
ダウンロードページはこちら
○ 「1日1単語」で、英語の読み書きがどんどんできるように!RISE English Course 英語カレンダーはA41枚で一週間分。これをプリントアウトして毎日1単語ずつ練習すれば、いつのまにかにほとんどどんな単語でも、すらすらと読み書きできるようになります。
○ 苦手を防ぎ、得意を伸ばす!ポイントは「音の足し算」!日本人が英語を苦手としがちな理由の1つとしてあげられるのが、「音に対する気づき」の不足、そして「音の足し算」への不慣れです。これに慣れれば、一見難しそうな単語もかんたんに読み書きできるようになります。 in ⇔ sin ⇔ sing ⇔ stings ⇔ string tea ⇔ eat ⇔ meat ⇔ team ⇔ steam
|
|
| ○ ご利用にあたって
・このカレンダーの著作権は「NPO法人リヴォルヴ学校教育研究所」にあります。
・このカレンダーは、非営利目的に限り自由に利用できます。ただし、そのままプリントアウト、コピーをする場合に限られます。部分利用、翻訳等は含まれません。 ・イラストには、マイクロソフト社が提供するクリップアートを一部加工して利用しています。 |
↑クリックするとサイトが開きます。 |
ダウンロードページはこちら
いっしょに使うと一層効果的!!
|
☆RISE 英語(4線)ノート☆ 好評発売中 |
|
|
☆RISE English 英語カン☆ 好評発売中 30年近くにわたり子ども達と向き合いそのつまずきを見つめてきた経験と,最新の研究成果に基づく「英語カン」には,「外国語に対するセンス( 勘 / 感 )」をみがき,「真に自然な方法」で「自ら学び取る力」,「外国語学習ストラテジー」を伸長するための工夫がこらされています。 |
|
|
☆不規則動詞プリント☆ 好評発売中 |
 |
お問い合わせはこちらから お問い合わせのページ
無料メルマガ「オノムの英語の学び方・教え方 vol.15」補足ブログ
英語は絶対に必要なのか?
12月25日に投稿した記事の中でふれた高校生、「英語の授業があると思うと、学校に行くのもいやになって…」といっていたA君が夜の教室に通い始めています。
一緒に見ている生徒もそうなのですが、二人とも‘tree’を‘free’と読んだり‘humidity’を‘human’と間違えたりします。
しかし二人ともとても勘が良く、数学では満点に近い点数を取っているそうです。
今年のセンター試験では、国語が非常に難しく、反対に英語のリスニングは簡単すぎて、ここで点数を稼いでいた生徒が不利になりました。
今の入試制度は平均的に点数が取れる生徒に有利であり、得意、不得意がはっきりしている生徒は不利になりがちです。
誰にでも得意、不得意はあるものです。だからこそ助け合いが必要になるのだとも思います。
これからの社会に求められるのは万能のリーダーではなく、自身の得意と不得意を理解し、自分らしさを上手に発揮できる人。
さらには、それぞれに異なる個性の集まりの中で、互いの良さを認め合える人ではないのでしょうか。
私も大学入試では、国語や社会では満点を取ったと記憶しています。
しかし英語や数学では点数が取れず、ようやく一校だけ補欠で合格できた私大に進学しました。
それでも私は、良い出会いに恵まれて、教師になることができただけよかったと思います。
ですがA君のように英語で大きくつまずいている子を見ると、かつての自分を思い出します。
現在の学校教育、そして入試制度は、このような子ども達の可能性の芽を、伸ばすどころか摘み取ってしまってはいないでしょうか。
こうして考えると、英語なんてできなくてもいいのではないかと思います。
さまざまな場面で、英語が必要となるのは確かです。
しかし企業の中で、会議を英語で行うなどという話を聞いていると、何か勘違いをしてはいないだろうかと思います。
日本で暮らす私達に、英語力は本当に必須なのでしょうか。
英語が、A君のような若者の自信や可能性を削いでしまっている。このような若者が全国にどれだけいるのだろうと考えると、英語をすべての子ども達に強いるようなことはすべきではないとも思えてきます。
中学や高校では、全員に英語にふれる機会を与えるにしても、入学試験の方法については見直すべき点があるのではないでしょうか。
少なくとも教師は、指導方法を根本から見直す必要があるのではないかと思います。
無料メルマガ「オノムの英語の学び方・教え方 vol.15 3.1.5 英語のテストに強くなる (5):長文問題に強くなる(後半)」
オノムの 英語の学び方 教え方【vol.15】◆◇◆ 2013年2月25日(月)発行
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
~ オノムの 英語の学び方 教え方 ~
――――――――――――――――――――――――――――― vol.15
どうしたら、苦手を克服し、英語が得意になれるのか?
英語の勉強方法、教え方に迷っているあなたに、長年、学習につまずきがちな
子ども達の指導にあたる筆者が、最新の学習理論に基づいた具体的な学習方法
をわかりやすくアドバイス!
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
3.1.5 英語のテストに強くなる (5):長文問題に強くなる(後半)
まだ寒い日が続きますが、陽ざしには春の気配も感じられるように
なってきましたね。みなさんはいかがお過ごしですか。
今回は最初に少しお知らせをさせてください。
当法人ではこのたび、英語の苦手を防ぎ得意を伸ばすための
「英単語カレンダー(無償です!)」を作成しました。
小中学生など入門者向けで1日1単語、これを1年間練習していただけば、
ほとんどどんな単語でも読み書きできるようになります。
当法人のWebサイトからダウンロードいただけます。
https://rise.gr.jp/manaby/revolve_kyouzai/calender_free
個人向けには3月1日スタート、
学校等でもご利用いただけるように4月8日スタート版も用意します。
これを利用いただくことで、
少しでも子ども達のつまずきを軽減できればと思います。
お知り合いにもご紹介いただければ幸いです。
さて、12月25日号の補足ブログでふれた高校生のA君も、
「英語の授業があると思うと、学校に行くのもいやになって…」と
言っていた一人でした。
今回は、そんな彼らの授業の様子を再現しながら、
先回お話しした読解のポイントを確認したいと思います。
課題としたのは、センター試験2007年本試験の第4問Aの問題です。
グラフを見ながら英文を読み、3つの質問に答えます。
Web上で「2007年センター英語」と検索していただき、
問題文を確認の上でご覧ください。
先回、長文読解でも「類推を働かせること」が大切とお話ししましたが、
この問題はグラフさえ読み取れれば、ほとんど本文を読まずとも正解できます。
折れ線グラフのタイトルは
‘Production of Packaged Soft Drinks:パックされたソフト・ドリンクの
‘production’です。
ここでA君は‘production’は読めても意味がわかりませんでしたので、
英語のままにしておきます。
グラフの下には日本語で、
「データ:全国清涼飲料工業会、『清涼飲料関係統計資料』2005」とあります。
2004年の時点で
第1位 = Tea drinks 第2位 = ?(X)とCoffee drinks(同量)
第4位 = ?(Y) 第5位 = Sports Drinks 第6位 = ?(Z) です。
問1は‘In the graph, which type of drinks does “X” stand for ?’、
要するに「‘Which …“X”?’:どれが“X”ですか」ということです。
私はまず
「“X, Y, Z”に入りそうなのは何だと思う?」と質問しました。
そこで出てきたのは、
「お茶? いや、どっちも‘Tea Drinks’に含まれるか?
じゃあ、炭酸系? あと、オレンジジュースとか?」という答えです。
「じゃあ、コーヒーと同量で第2位の“X”はその内のどれだと思う?」
「やっぱり、炭酸でしょう」
「じゃあ、炭酸飲料って英語で何と言うの?」
「いや、それがわからない」
単語がわからなければ長文問題は解けないという発想では、ここでストップですが…。
「それじゃ、選択肢の中から‘炭酸飲料’を探してみてください」
するとA君はすぐに、「① Carbonated drinks」を指さし、
「カーボン、そうカーボンだ」と言いました。
私はホワイトボードに「CO2」と書き、「二酸化炭素だよね」としました。
第2問は、4つの英文の中から本文の内容に合ったものを選ぶ問題です。A君らは4つの英文を、
(1) Carbonated drinks were still leading in popularity in 2014.
(2014年、炭酸飲料はleading している)
(2) Production of coffee drinks had increased dramatically
since their introduction.
(コーヒーの‘production’はドラマチックに‘increase’している)
(3) Production of fruit juices declined from 1987.
(フルーツジュースの‘production’は1987年から減少している)
(4) Vegetable juices took over a considerable portion of the soft drinks market.
(野菜ジュースは清涼飲料マーケットの‘considerable portion’を‘took over’している)
と読んだ結果、グラフも見ながら
「(1)と(2)はない。リードしていないし、‘dramatically’ではない。
(4)も何となくなさそう。…たぶん、(3)が正解」と、予測しました。
そこで私は、
「③で‘減少する’って言ったけど、それはどの単語を見て言ったの?」
「‘decline’ですか」
「それは自信がある?」
「あまりないけど、音からして何となく減少していそうな感じ」
「それならもし、第4位に落ちた‘Y’が‘fruit juice’なら正解だね」として、
ここで初めて本文を読んで‘fruit juice’を探すように指示しました。
本文中には10行目に、
Fruit juice had fallen to fourth … with a drop in production …
とあり、‘fallen:落ちる、fallの過去分詞’などから
彼の推測が正しかったことがわかります。
先回はもう1つのポイントとして、「S + V + Oを確認すること」を挙げました。
実際の指導場面では、「主語はどれ?」「‘何が、どうした’っていっているの?」と
繰り返し確認をしています。
‘decline:下に(de)曲げる(cline)→断る、下落する’のような
語に対するストラテジーを伸ばすためには、
日頃から語根(cline)や接頭辞(de)、接尾辞、
さらに「音からの印象と意味」との相関性などについても再三指導をしています。
先回、そして今回とお話ししていることの1つは、
単語を丸暗記するような学習方法がいかに非効率的かということです。
これと同様に、語根や接頭辞、接尾辞を暗記することもお勧めしません。
これらを取り上げるのは、単語を分析的に捉える力をつけ、
場面や文脈から書かれた内容を推測する力を伸ばすためです。
このような練習を繰り返していけば、無理に暗記しようとなどしなくても、
いつのまにか必要な知識が身についてしまうものです。
なお、誤解のないようにしておきたいと思いますが、
私は「辞書が不必要」だと言っているのではありません。
私の授業ではまめに辞書をひかせます。
しかし異なるのは、それが単語の意味を調べるためではなく、
推測した意味を確認するためであるということです。
得てして予想は外れますが、大切なのは正否ではなく、
自分で考えるということです。
当法人のブログには、
今回の記事のメルマガの補足記事も載せましたので、ぜひこちらもご覧ください。https://rise.gr.jp/archives/7844
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
《今日のポイント》
・ 意味がわからない単語は、S + V + Oを確認し、
「‘pollution’が‘sea animals’を‘harm’している」などとして、
場面や文脈から類推を働かせて読むようにする。
・「単語を覚えなきゃ、長文問題はできるようにならない」ではなく、
上のような方法でまとまった英文を読むことを繰り返し、
「読むことで、ボキャブラリーを増やす」ようにする。
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
次回は「日本語と英語:異なる点と似ている点(前半)」をお届けします。
☆ ご意見・ご感想はこちら ☆
───┬───────────
└─→ https://rise.gr.jp/contact
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
メールマガジン「オノムの 英語の学び方 教え方」
○発行責任者:NPO法人リヴォルヴ学校教育研究所
○公式サイト:https://rise.gr.jp/
○問い合わせ:https://rise.gr.jp/contact
○登録・解除:http://www.mag2.com/m/0001574644.html
「LED✩光りもの実験✩」教室が開催されました(ライズ学園日記 カルチャー教室)

本日の理科実験教室の講師は、久保 利加子さんです!
お題は、「光りもの実験」。LEDの仕組みについても学びました。

久保さんのリュックの中から、いろんな色のぬいぐるみやスリッパ(!)が出てきて、ホワイトボードに貼りついています。
暗くして赤い光を当てると色がわからなくなって・・・、
また電気をつけるとちゃんとわかる。
電気や太陽の光(白色光)には、いろいろな色の光が混ざっているから、それぞれの色が見えるんだそうです。

LEDと電球の違いを信号機で実感。
Ks君とYs君が、実演に協力してくれました。
久保さんが、本当の信号機に使われている電球を持ってきてくれたのでびっくりでした!

そのほかにも、
赤い羽根で、指が透けて見える実験をしたり、
分光シートで蛍光灯を見てみたり(虹色に見えます)、
いろんな実験を通して、光のこと、LEDのことを知りました。


久保さんのアイディア力で作られた、身近な材料を使っての素敵なイルミネーション工作も体験。
プラスチックのカップに絵を書いて、中に3色LEDライトをゴムでつるし、ゆらゆら揺れるイルミネーション。
アルミカップを下に置けば、さらにキラキラします✩
最後に一斉に点灯させたイルミネーションの様子は、下記動画をご覧ください。
盛り上がりました〜。
久保さん、わかりやすく楽しい理科教室をありがとうございました。
無料メルマガ「オノムの英語の学び方・教え方 vol.14」〜英語のテストに強くなる (4):長文問題に強くなる(前半)〜
小野村の無料メルマガ記事を、こちらのブログでも少しずつ紹介させていただきます。
Facebookコメント、大歓迎です。
好評につき、バックナンバーも当法人サイトでまとめて読んでいただけるようにしていく予定です。
(現在バックナンバーはこちらから読めます)
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
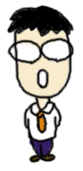
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
オノムの 英語の学び方 教え方【vol.14】◆◇◆ 2013年2月16日(土)発行
――――――――――――――――――――――――――――― vol.14
どうしたら、苦手を克服し、英語が得意になれるのか?
英語の勉強方法、教え方に迷っているあなたに、長年、学習につまずきがちな
子ども達の指導にあたる筆者が、最新の学習理論に基づいた具体的な学習方法
をわかりやすくアドバイス!
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
3.1.4 英語のテストに強くなる (4):長文問題に強くなる(前半)
英語が苦手だという人からは、よく、「単語が覚えられない」と聞きます。
「単語を覚えなきゃ、長文問題はできるようにならない」と思い、
単語集を買うなどして練習をする。
それでもなかなか頭に入らないから英語が嫌いになり、
ますます苦手になってしまう。
実は私もそうだったのですが、
このような悪循環に陥っている人は少なくないと思います。
昨年末から「英語のテストに強くなる」をテーマとしてお話してきました。
その最終話として「長文読解問題」を2回に分けてとりあげますが、
今回は単語力について、発想の転換をして「まとまった英文を読みながら、
単語力を養う方法」についてお話したいと思います。
そこでまず、
「カタカナ語はすぐに覚えられるのに、なぜ英単語は覚えられないのか」
ということを考えてみましょう。
たとえば「汚染が海の生物にダメージを与えている」などと聞いたときに、
「ダメージ」の意味をカタカナ語辞典で調べたという人は少ないと思います。
しかし‘Pollution harms sea animals’のような文中で
‘harm:害する’を聞いたり読んだりした場合は、
多くの人が辞書を引いて意味を調べようとします。
「ダメージ」などはすぐに覚えられるのに、
ノートに何回書いても覚えられないということにもなりがちです。
最近の研究では、音から受ける印象によって、
語の覚えやすさに違いが生じることがわかってきています。
「ダメージ」の音は日本語の「ダメ」にも通じるものがありますから、
‘harm:害する’にくらべて覚えやすいということも考えられます。
しかし、理由はそれだけではありません。
その他の理由としてまず考えられるのは、学ぶ姿勢の違いです。
初めてのカタカナ語にふれたとき、私達はまずその意味を場面や文脈から類推して理解しようとします。
つまり、自分で考えているのです。
ところが英単語の場合は、すぐに辞書に頼ってしまい
自分で考えようとしない。
受け身の姿勢になっています。
迷いながらでも自分で行けば覚えられる道も、
誰かの助手席に乗って出かけたのではなかなか覚えられません。
自分で運転していても、カーナビに任せっきりにしてしまえば
同じことです。
ここで私の生年月日をお伝えしても、
みなさんはすぐに忘れてしまうでしょう。
しかし、大好きな人の生年月日だったら、
一度聞いただけでも忘れないということもあります。
私達の脳は、自分自身で考えたこと、自分に必要だと感じたことは
よく覚えているものです。
その一方で、「テストのために覚えなきゃ」とは思っていても、
脳が「本当に」必要だと感じてはいないこと、自分自身で
考えていないことはなかなか記憶に残らないものです。
日本語にふれる時間を100とすると、
外国語としての英語にふれる時間はその5%にも達しないともお話ししました。
「苦手、嫌い」となれば、その時間はもっと減ってしまうのが
普通ですからなおさらです。
しかし「ダメージ」のようなカタカナ語も、
毎日、繰り返し聞いているわけではありませんし、
覚えようとして練習をしているわけでもありません。
それでも、たくさんのカタカナ語を身につけられる私達が、
‘harm’くらいの単語を覚えられないはずがないのですが…。
では、どうしたらよいか。
先回の「並べかえ(語順整序)問題に強くなる」の中でもふれましたが、
‘Pollution harms sea animals …’のような文は、
S + V + Oを確認し、
「‘pollution’が‘sea animals’を‘harm’している」とします。
翻訳家や通訳を目指すのでなければ、
‘pollution’や‘harm’を日本語にできなかったとしても
問題ではありません。
しかしここで「‘harm’ってどういう意味?」と尋ねると、
「ほら、その、何ていうか…こんな感じ?」といって
手振り身振りで答えてくれる生徒もいます。
私はそれで正解とし、ときによっては「辞書で確認してみようか」
とします。
すると興味深いことに、まずほとんどの生徒が、
「あっ!(Aha!)」と声をあげます。
これがいわゆる「アハー体験」です。
最近よく知られるようになった「アハー体験」ですが、
これは心理学辞典にも載っている専門用語です。
以前にも、「あっ! そういうこと」と気づけるようにすることが
大切だと書きましたが、このような体験を通して学んだことは、
記憶にも残りやすいものです。
授業の中で「‘leave’の意味は?」と聞いたところ、
「猿」と答えた生徒もいました。
予習を忘れたその生徒は休み時間に友達に聞いて、
「去る」と言われたのを「猿」と勘違いしてしまったようです。
笑い話のようですが、これは見過ごすことのできない問題です。
多くの学校では相変わらず、単語の予習をさせ、
文法事項を確認した上で、英文を日本文に直す
といったことが行われています。
しかしこのような学習方法では、
どうしても辞書に頼りがちになり、
読解も受け身になりがちです。
これでは力もつきません。
‘Pollution harms sea animals …’の前後に、
‘… pollution are causing a lot of damage to human health’
などとあれば、
「‘pollution’は人々の健康に多大な‘ダメージ’を‘cause’している」
とすることで‘pollution:汚染’だと推測ができます。
とすれば自ずと、‘harm’の意味も見当がつきます。
内容を理解するということでは、
「読むこと」も「聞くこと」と同じです。
したがって、リスニング問題の際にも挙げた「場面や文脈から類推を働かせること=自分で考えること」の大切さは、
読解問題でも同様です。
長文問題に強くなるためにも、辞書に頼りすぎることなく、
類推を働かせながら読む習慣をつけることが大切です。
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
《今日のポイント》
・ 意味がわからない単語は、S + V + Oを確認し、
「‘pollution’が‘sea animals’を‘harm’している」などとして、
場面や文脈から類推を働かせて読むようにする。
・ 「単語を覚えなきゃ、長文問題はできるようにならない」ではなく、
上のような方法でまとまった英文を読むことを繰り返し、
「読むことで、ボキャブラリーを増やす」ようにする。
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
次回は「英語のテストに強くなる (4):長文読解問題に強くなる(後半)」を
お届けします。
☆ ご意見・ご感想はこちら ☆
───┬───────────
└─→ https://rise.gr.jp/contact
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
太鼓ワークショップが開催されました(ライズ学園日記 カルチャー教室)
幻想的な「田井ミュージアム」のステージで、ライズ学園のカルチャー教室として太鼓ワークショップが開催されました。
講師は、NPO法人自然生クラブ代表 柳瀬 敬さんです。
柳瀬さんの太鼓ワークショップは、とにかく太鼓をたたき続けるところから始まります。
そのなかでも、一人ひとりのたたき方が影響しあって、いろいろなリズムや強弱が生まれてくるから不思議です。

中学生Y君。沖縄太鼓を2つも確保して、勢いよくたたいているうちに、寝ながら打法!
自分のリズムでたたき続けます。
いつの間にか30分経過。
「あ~つかれた~」とみんなで寝転がって、柳瀬さんとお話した後には、柳瀬さんのたたき方を真似して太鼓をたたいてみました。
これがけっこう大変ですが、おもしろいのです。
1時間のワークショップはあっという間に終わって、帰りのバスの中では元気にしりとりして帰りました。
人間の内臓一つ一つは、ちゃんとリズムを打っていて、そんなリズムを波打たせる太鼓には自律神経を高める力があるそうです。
生きる力がわいてくることを実感した太鼓ワークショップでした!
柳瀬さんありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
宮城県東松島市立野蒜小学校さんへ花苗をお届けしました!~被災地支援活動~
昨年5月に「書き損じハガキを集めて東日本大震災被災地の子ども達に“花苗”を送ろう」プロジェクトで、支援先の宮城県東松島市立野蒜小学校さんに花苗をお届けしました。野蒜小学校さんから写真が届きましたので、ご報告いたします。
野蒜小学校さんは、津波で大きな被害に遭い、校舎も使えなくなってしまいました。そのため、仮設プレハブ校舎で授業を再開しています。
このプロジェクトのご案内をした際に、花壇がないのでプランターに花を植えたいとおっしゃいました。
そこで、プランター40個、培養土 20袋、ベコニア 160株 をお送りしました。
お送りしたプランターに、子ども達が絵を描き、そこに花を植えたそうです。


野蒜小学校の先生からいただいたメールを紹介させていただきます。
「昨年は、温かいご支援をいただきたいへんありがとうございました。
本校では異学年児童で構成するたてわり班ごとに、プランターに思い思いの絵を描き、そのプランターにベコニアの苗を植えました。
そのプランターは、レインボーレインという子どもたちがスクールバスに乗って帰る際、集合する場所に並べ、花を見ては癒されていました。また、水やり等の花の世話も、たてわり班ごとに声を掛け合って行い異学年児童の交流の機会にもなりました。
このように、本校では、将来復興の担い手となる子ども同士のつながりを持つ活動を多く行っています。ご支援いただいた花やプランターは、その活動に有効に活用させていただきました。ありがとうございます。」
学校が今までと同じような環境を取り戻すには、長い時間がかかると思います。私達は、ほんの少しでも細く長くお手伝いができればと思っています。
今年も「書き損じハガキを集めて東日本大震災被災地の子ども達に“花苗”を送ろう」プロジェクト は続けています。
書き損じたり、出さなかったりした年賀状がお手元にありましたら、是非お送りください。
今年の春もたくさんの花苗を子ども達に届けましょう!!
「オノムの英語の学び方・教え方」〜英語のテストに強くなる〜補足ブログをアップしました
受験シーズン真っただ中です。しかしテストで出題されている問題の中には「どうしてこの問題なの?」と疑問を感じさせるものも少なくありません。
英語ではコミュニケーション重視といいながら、「英語力」ではなく「注意力」や「根気」を見ようとしているのではないか、と思われるような出題も多く目にします。
今回のセンター試験では、アクセントの問題で出題された16単語の内、5単語がメルマガの中でふれた(パターンの)単語でした。高校入試ではもっと高い確率で出題予想が可能ですから、点数が取りやすい問題として「お得感」はあります。しかし「それで本当にいいのか」とも思います。
さらにセンター試験では、単語は‘qual-i-ty’と分節されない状態で提示されています。‘quality’は先頭にアクセントがありますが、これを‘※qu-al-i-ty’としてしまえば第二音節にアクセントがあると判断してしまうことにもなりかねません。
今、単語の分節方法をきちんと教えている高校はどれくらいあるのでしょう。あなたは学校で、単語の分節法について指導を受けた記憶がありますか?教えられてもいないのにこのような出題がされているのだとしたら、これは不当な問題以外の何ものでもありません。
講演会などで「どうしてテストをするのですか?」と質問すると、戸惑われたような表情を見せる先生も少なくありません。「テストがあるから、テストをつくる」というようなことにはなっていないでしょうか。テストを行う際には、「なぜ、何を目的に行うのか」「どのような力を試そうとしているのか(どのような力が求められているのか)」を確認する必要があります。
テストは、生徒の到達度を測るだけでなく、指導の成否を評価するためのものでもあります。平均点が40点にも達しないようなテストを実施して「生徒の努力が足りない」「厳しくしなければ、生徒は努力しない」などと言っている先生もいますが、そのような先生は、生徒の努力不足と同時に自身の指導力の不足を露呈していることに気づいているのでしょうか。評価が40点にも達しないようなレストランに、お金を払って食事に行こうという人がいるでしょうか。
求める力を正確に測ることができたのか否か、テスト自体が妥当で信頼がおけるものであったかを検証する必要もあります。先生方には、生徒に通知表を渡すだけでなく、せめて問題別に正答率ぐらいは算出してほしいと思いますが、これを行っている先生はどれだけいるでしょう。忙しいというのもわかりますが、コンピュータを上手に使えば、普通に採点するのとほとんど同じ時間でより精細な分析を行うことも可能です。
ある専門書に、「本当に良いテストは、これも、本当に良い授業と相まって、生徒の力を伸長する」と書かれてあったのを印象強く覚えています。ちょっと辛辣ですが「無責任なテストが‘落ちこぼれ’を作る」と題された名著もあります。しかし今、大学の教職課程で、テストの作成方法やテスト自体の妥当性や信頼性、実用性についての評価方法について、きちんと指導を受けている学生はどれほどいるのでしょう。
生協で販売!!「ひらがなれんしゅうちょう」&「英語れんしゅうちょう」
リヴォルヴ教材の中でも根強い人気のある「ひらがなれんしゅうちょう」と「ABC英語れんしゅうちょう」が 、生協を通じてご購入いただけます。
今回お取り扱いいただくのは、コープきんき、コープこうべ、CSねっと です。
1月のカタログ「キャロット」に掲載されていますので、是非ご購入ください。
【もじのかたちを覚えるためのひらがなれんしゅうちょう】
ひらがなを50音順に覚えるのではなく、かたちの似た文字ごとに覚えるというこれまでにないユニークなれんしゅうちょうです。
はじめてひらがなを練習するお子さんや、これまでの練習帳ではなかなかひらがなを覚えられなかったお子さんにお勧めします。また、ひらがなは書けるけれど、きれいなひらがなが書けるようになりたいお子さんにもお勧めです。お孫さんへのプレゼントにも最適です。
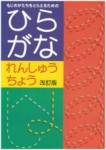 ☆サンプルやお使いいただいた方の感想はこちらから
☆サンプルやお使いいただいた方の感想はこちらから
【よめる かける ABC英語れんしゅうちょう】
「見ておぼえるためのヒント」や「聞いておぼえるためのヒント」を使って、楽しみながらアルファベットが覚えられるようにしてあります。また「音の足し算」では、英語を読んだり書いたりできるようになるためのコツを、いつの間にか身につけられるような工夫がしてあります。
はじめて英語を学習するというお子さんはもちろん、英語を苦手とする中学生や高校生の学習にもお役立ていただける内容となっております。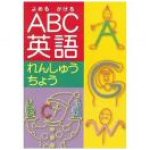 ☆サンプルやお使いいただいた方の感想はこちらから
☆サンプルやお使いいただいた方の感想はこちらから
ライズタイム「ライフラインがストップしたら?」「災害伝言ダイヤルの使い方」を実施しました
ライズタイムでは、災害時のためのワークを一年通して行ってきました。
ライズ学園の周囲を歩き、ハザードマップを作成したり、天災の時の身の守り方などをみんなで話合いながら学んできました。
今回のライズタイムは 「ライフラインがストップしたら何が必要になるか?」をみんなで考えました。
2チームにわかれ、自分の意見をポストイットに書いて、大きな模造紙にぺたぺたと貼っていきます。
水道がストップしたらどうする?の所では、
KSさんの「もしもの時のために、ライズに飲料水を置いておけばいいんだ。」と、非常用に水を備蓄しておくことを提案。
Rさんは、「自動販売機からとってくる。」
と一言。災害時には、飲料水が無料で提供される自販機もあるそうです。Rさんの情報量には驚かされます。
「水が使えないということは、トイレも使えないよね。」とのスタッフの言葉に、「我慢する!」「簡易トイレをつくる!」など、いろいろな意見が出てきます。
電気がストップした時には、
「ライズにある理科の実験道具を使って、がんばる!」とKAさん
暖房器具が使えずに、寒いときはどうする?のところでは、
「みんなで、集まってあたたまる。」とKTさん。
模造紙には、いっぱいのポストイットが貼られていきます。
その後、二つのグループで話合われたことを発表していきます。


1つ目のグループの司会はYKさん。
はきはきと、簡潔にまとめて発表していきます。
「水道が使えないときは、~の意見がでました。」
随時、グループの友達が補足もしながら、上手に発表していました。
2つ目のグループの司会はKTさん。
楽しい冗談をまじえながら、流暢に発表していきます。
聞いている子どもたちも、楽しい雰囲気につられて笑顔になっていました。
ライズの電話をオンフックにして、実際にメッセージを入れたり聞いたりしてみました。
ライフラインがストップした時にどうするか?
次回は、みんなで考えたことの中から、ライズ学園でできることを準備していきます。











